筆者は21世紀COE研究員としてラオス・フィールド・ステーション(以下LFS)を拠点に調査研究活動を開始したが、2004年3〜4月におけるLFSの活動内容ならびに21世紀COEプログラムの一環として筆者自身が行う個別研究の計画につき報告したい。
21世紀COEプログラム・ラオス研究班は、2003年度の活動の締めくくりとして、ワークショップ「ラオスにおける生物資源利用とその変容」を開催した。ワークショップには、ラオス・日本双方から研究者・学生等23名が参加し、活発な議論が繰り広げられた。概要は以下の通りである。
なお、LFSは現地研究者との共同研究促進をその活動の大きな柱の一つとしているが、ラオス国立大学林学部を卒業した若手研究者Saysana 氏が、ASAFAS大学院生の小坂さんとともに共同研究を行い、その成果を本ワークショップにおいて発表したことは、カウンターパートとの協力体制構築が軌道に乗りつつあることを示していると言えよう。
LFSでは臨地調査のために来訪した研究者・院生等に対して適宜、必要とされる支援を行っている。2004年3〜4月におけるLFS来訪者は次の通り。
(3)個別研究の計画 |


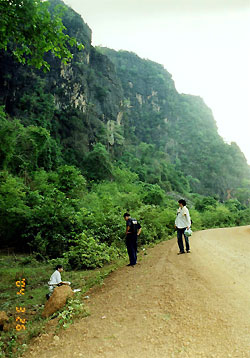

 21世紀COEプログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」
21世紀COEプログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」