| ミャンマー・フィールド・ステーション活動報告(4) |
| 大西信弘 (21世紀COE研究員) |
これまで行ってきたラカイン州、グワでの調査報告のため、2004年3月16、17日にカウンターパート機関であるSEAMEO-CHATにおいて、Change of Rural Society and Local Agro-ecological Knowledge in Myanmar と題するワークショップを開催した。
今回のプログラムでは、以下に示すとおり12題の発表があった。ミャンマーから7名、日本からは5名の発表者があった。これまでのラカイン州での総合研究プロジェクトは、歴史学、地理学、経済学、農学、動物学、植物学の専門研究者たちが共同研究を進めてきた。このプロジェクトでは、これら異分野を連携させるため、定期市における資源の流通、交換を通して、村の中での資源の流れと人の関わりを探ることで、各専門分野が連携を持ちながら研究を進めることを狙った。定期市を中心において多角的な視点からのアプローチがなされたという点では、実りあるプロジェクトであったといえよう。


このような( Program) 発表から、Integrated Area Studies という観点でインスピレーションを受けた聴衆もいたかもしれない。しかし、これだけでは総合化としては不十分なことは明白で、Integrated Area Studies に対する回答を明示できなかったことが、今回のワークショップの最大の反省点である。確かに文系分野と理系分野が共同することで、お互いの影響を受けながら研究が進められてはきたが、異分野の研究者が共同研究を行う意味は、単に多様な視点をもたらすだけではない。それぞれの分野がリファインしてきた理論を異分野で応用することによって、理論の統合がおこなわれるだろう。そして、細分化された研究分野の再編と相互の位置づけが行われ、それぞれの学問分野が共通した基盤のもとに対象を理解することが可能になるはずだ。このことこそが重要だと考えている。この点は、次回のワークショップへ向けた反省点としたい。 Program) 発表から、Integrated Area Studies という観点でインスピレーションを受けた聴衆もいたかもしれない。しかし、これだけでは総合化としては不十分なことは明白で、Integrated Area Studies に対する回答を明示できなかったことが、今回のワークショップの最大の反省点である。確かに文系分野と理系分野が共同することで、お互いの影響を受けながら研究が進められてはきたが、異分野の研究者が共同研究を行う意味は、単に多様な視点をもたらすだけではない。それぞれの分野がリファインしてきた理論を異分野で応用することによって、理論の統合がおこなわれるだろう。そして、細分化された研究分野の再編と相互の位置づけが行われ、それぞれの学問分野が共通した基盤のもとに対象を理解することが可能になるはずだ。このことこそが重要だと考えている。この点は、次回のワークショップへ向けた反省点としたい。
報告 << No.3
| No.5 >>
| 
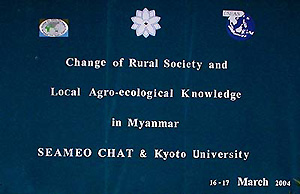


 21世紀COEプログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」
21世紀COEプログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」